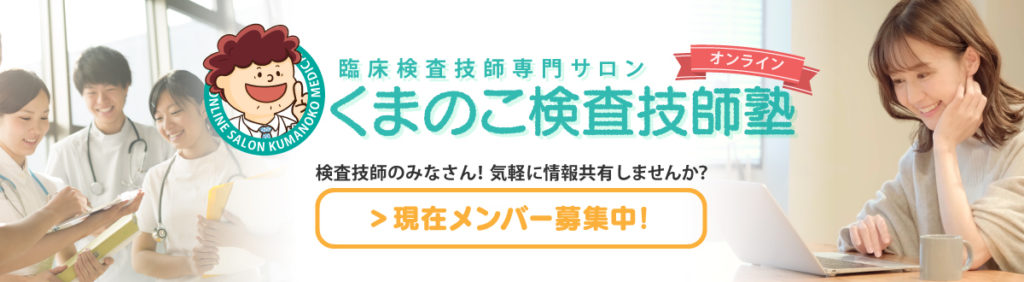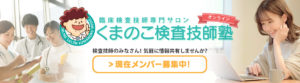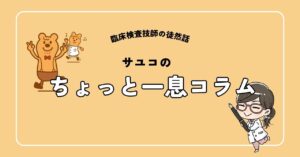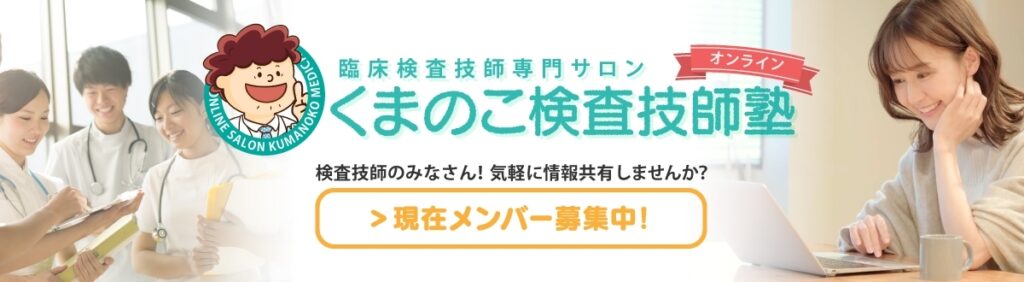大変だけど、価値がある!超音波検査士になって良かったこと【後編】#2

こんにちは。
臨床検査技師かつ医療系ライターのサユコです。
臨床検査技師にまつわる様々なテーマを取り扱ったコラムを書いています。
前回は超音波検査士について、筆者の試験受験までの道のりを振り返っていました。
今回はその続きです。
学会の必要在籍年数を満たし、やっと適切な症例を集め…ここからも一苦労、二苦労ありました。

サインを貰える専門医のあてがない!
受験には、超音波専門医のサインが必要です。
やっと症例を集めても、勤務先に専門医が在籍していないと「誰にお願いすればいいんだろう…」と途方に暮れることになります。
私はここでもつまずきました。
エコーの読影も認定医が行っていなかったからです。
とにかく伝手を辿るしかなく、レポートの準備と並行して知り合いの医師や勤務先の先生方に知り合いにいないかを聞いて回りました。
結局、施設長の先生のお知り合いを紹介して頂き、菓子折りを持ってお願いに行きました。
合否はサインした先生にも伝わるそうです。
もしも落ちてしまったら、サインをお願いした先生と施設長のどちらにも顔向けできません。
万一落ちたらどんな顔をして出勤すればいいかわからず、物凄いプレッシャーでした。
基礎分野になじみがない!
超音波検査士の筆記試験は、領域ごとの【臨床分野】と共通の【基礎分野】に分かれています。
基礎はほとんどが超音波装置の基礎・エコーの原理なので、内容は物理的な要素が強いです。
私は特に抵抗がなく、大学でも教養で物理が必修だったので「懐かしいかも」と思ったくらいでした。
でも、周りの受験者と話した感じでは「物理は苦手!」と抵抗がある人が結構いるようですね。
一緒に受験した同僚の1人と後に受験したもう1人は、基礎分野に苦手意識が強くて苦労していました。
計算問題もありますし、物理の要素が入ってくるので苦手な人は本当に拒否反応が出るようです。
臨床検査技師になるための勉強としての物理は医用工学で少し触るくらいですが、ちょっと出題範囲が違います。
今はオンラインで色々な基礎講座の対策を受験できるので「独学では手に負えない」となったらそちらに頼る方が早いと思います。
臨床も勉強しなければいけないので、基礎に割く時間はなるべく短くしたほうがいいです。
今年からくまのこ検査技師塾でも「超音波医学講座(基礎)」のセミナーが始まるようなので、苦手意識がある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
オンラインで一から解説・問題演習をする様なので、1人で問題集を前に考え込むよりよっぽど効率的です。
また塾が運営するオンラインサロンでも「超音波検査士対策」のスレッドがありますので、ぜひサロンも有効活用しましょう。
私も入会していますが、非常に勉強になっています。
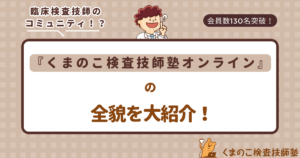
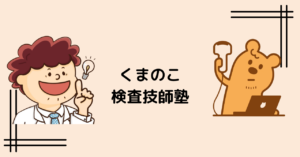
いろいろありましたが、私自身や周りの受験者が困っていたのは大体こんなことでした。
「みんな何かしら乗り越えて準備しているんだから私も頑張ろう!」と思った記憶があります。
それでも、諦めずに超音波検査士になって良かったこと

症例は中々いいものに出会わないし、サインして頂く専門医のあてはないし…で紆余曲折ありましたが、私はそれでも諦めずに受験して(合格して)良かったです。
主な理由は3つあります。
よく言われていることかもしれませんが、実際に体験して納得しました。
①試験の準備がルーチンに活かせる
私が勤務する健診施設では、所見に対して自分で考えるカテゴリ判定を添えてレポート提出を行っています。
実際に判定するのは読影の先生ですが、検査担当技師として「なぜその疾患、カテゴリと推測したのか」伝わるような写真を撮るように心がけています。
これは超音波検査士のレポートに求められることと同じです。
さらに、試験対策としてカテゴリの条件も全て覚えなければいけませんでした。
ややこしいものに苦労しながらも頭に叩き込んだ結果、実際に検査しながら瞬時にカテゴリまで予想して「じゃあこのカットも追加できるといいな」など考えられるようになりました。
実際、試験受験後に読影の先生に「写真の精度が上がった」と言われたことは自信につながりました。
健診領域しか受験経験がないため他の領域がわからないのですが、同じようにルーチンに結び付く知識が身に着くのではないかと思っています。
②転職に有利、お給料もUPしやすい
特に健診センターでは「超音波検査士歓迎」や「資格手当あり」の施設が多いです。
パートの時給も高くなりがちな傾向にあります。
私は超音波検査士をとった後に転職エージェントのお世話になったことがありますが、「超音波検査士をお持ちなら」と色々な施設を勧められました。
それだけ先方に売り込みやすく、需要があったということでしょう。
③一定の知識と技術を持っていることの証明になる
実際の認定試験で技術チェックはされないので何とも言えないところではありますが、最低限の「伝わる写真を撮ってレポートが記載できる」ことと「筆記試験に合格できるレベルの知識がある」ことは証明できるのではないかと思います。
実際に、面接の場で「(超音波)検査士持ってるなら大丈夫だと思うけど」と言われたことが数回あります。
その経験からも「超音波検査士の資格を持っているだけで、エコーの知識と技術について一定の評価を頂いている」と感じました。
ただ、自分の実力に対するハードルもその分高くなります。
思っていた以上に超音波検査士の効力は大きかったです。
だからこそ、「資格を持っててもこんな写真・レポートなの…?」と思われたくはありません。
まだまだ勉強することばかりではあるものの「超音波検査士」の名に恥ずかしくないように、日々の努力は欠かせません。
以上が、私の経験を踏まえたお話でした。

学会在籍期間、症例数の不足、サインしてくれる医師が見つからない、試験を受けるまでにもハードルが多い試験です。
でも、色々な面から取る価値がある、取って良かった資格だと思っています。
「超音波検査士、取りたいけど…」
と思っている方も、どうかあきらめずにコツコツ準備して挑戦して頂きたいです。
地道に積み重ねていれば、チャンスはいきなりやってくるもの。
私にもできたんだから、きっとあなたもできるはずです!
一児の母。
大学の検査技術学専攻を卒業した後、大学病院→個人クリニック→健診施設と勤務。
超音波検査士(健診領域)を取得したものの、まだまだ勉強中。
現在は検査技師かつ医療系ライターとして、フリーで働いています!

【現在会員数150名突破!】
臨床検査技師のためのオンラインサロン『くまのこ臨床検査技師塾オンライン』も運営中です。
学生も大歓迎!
他のコメディカルの方も入会可能です!
*1か月無料期間あり!
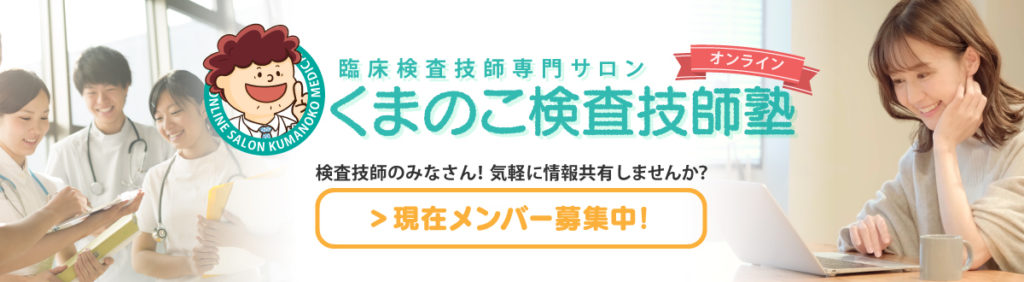
【現在会員数150名突破!】
臨床検査技師のためのオンラインサロン『くまのこ臨床検査技師塾オンライン』も運営中です。
学生も大歓迎!
他のコメディカルの方も入会可能です!
*1か月無料期間あり!